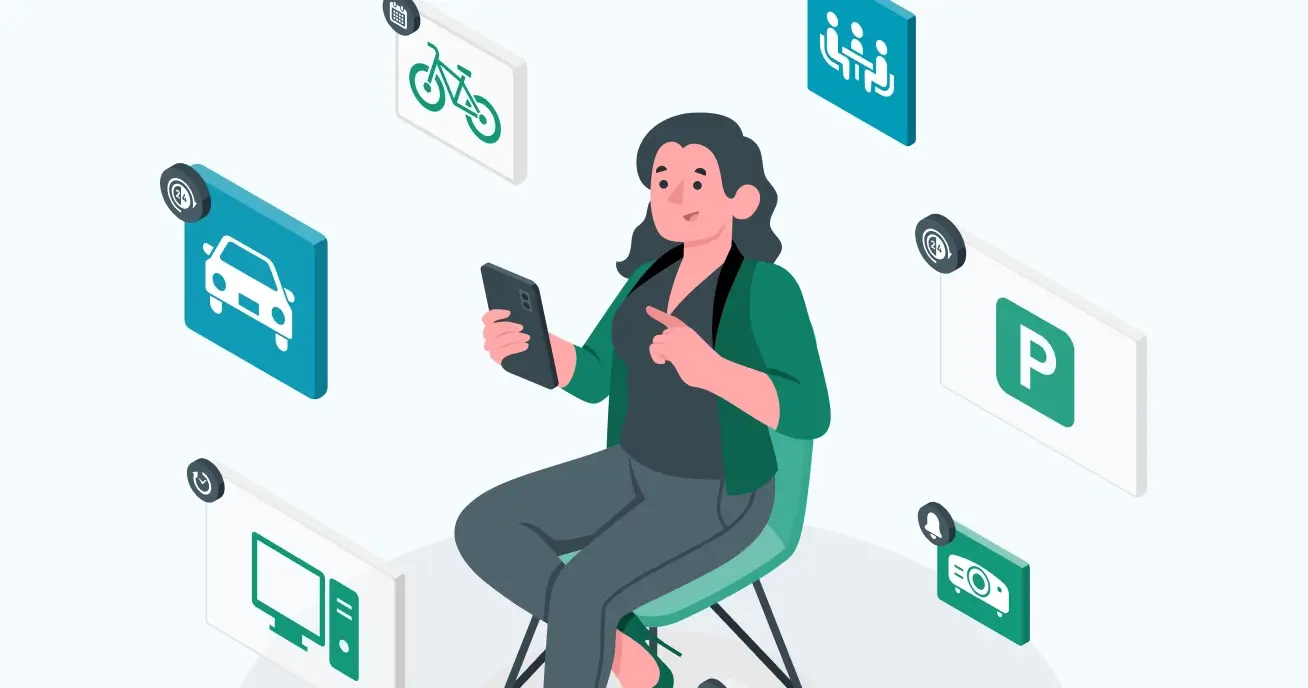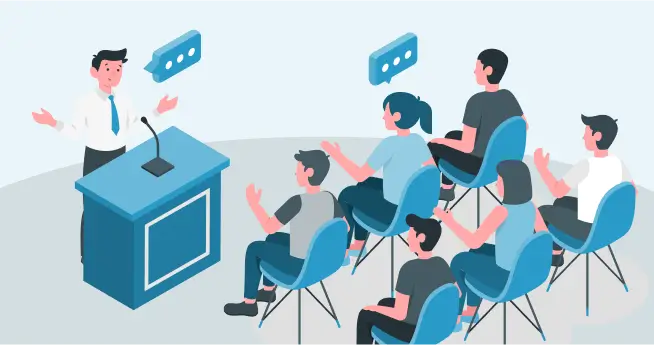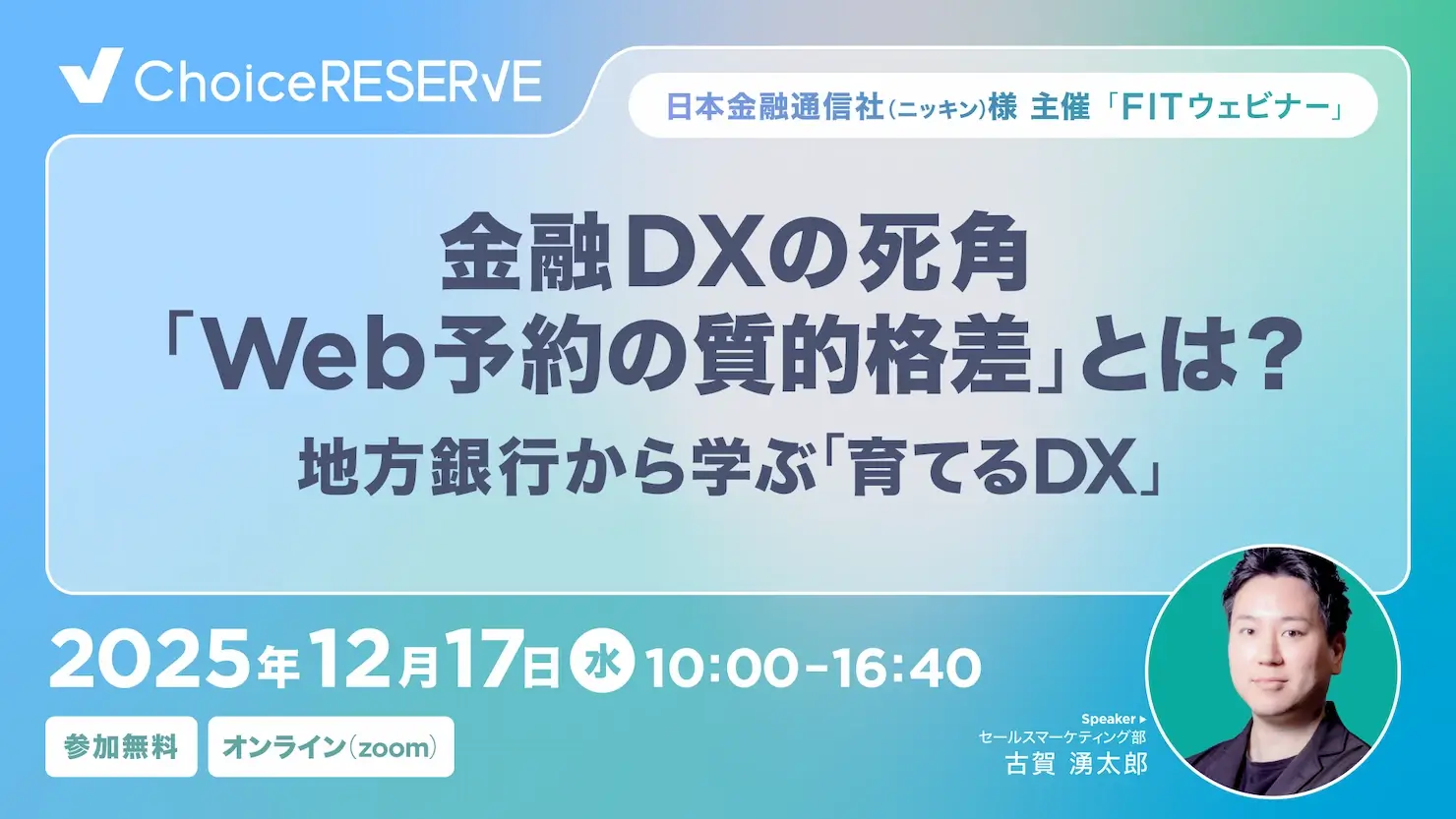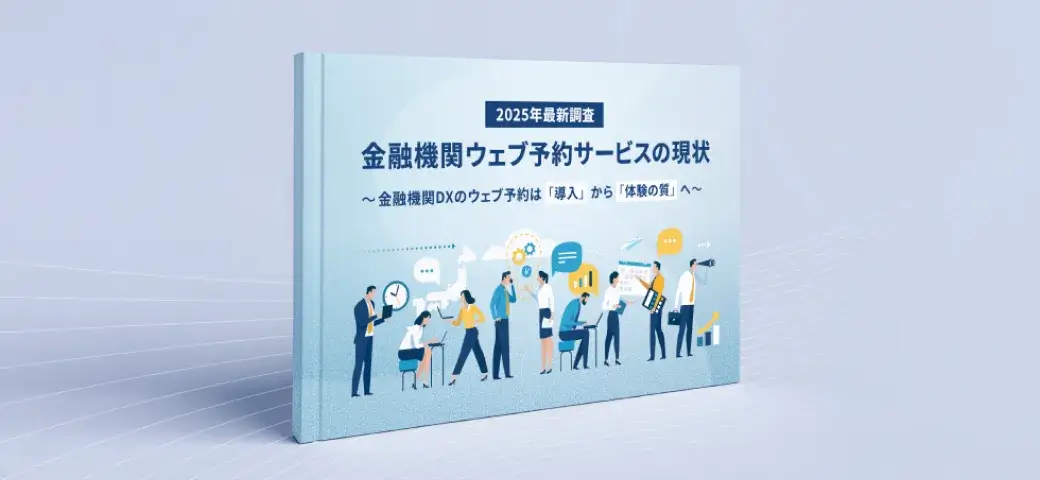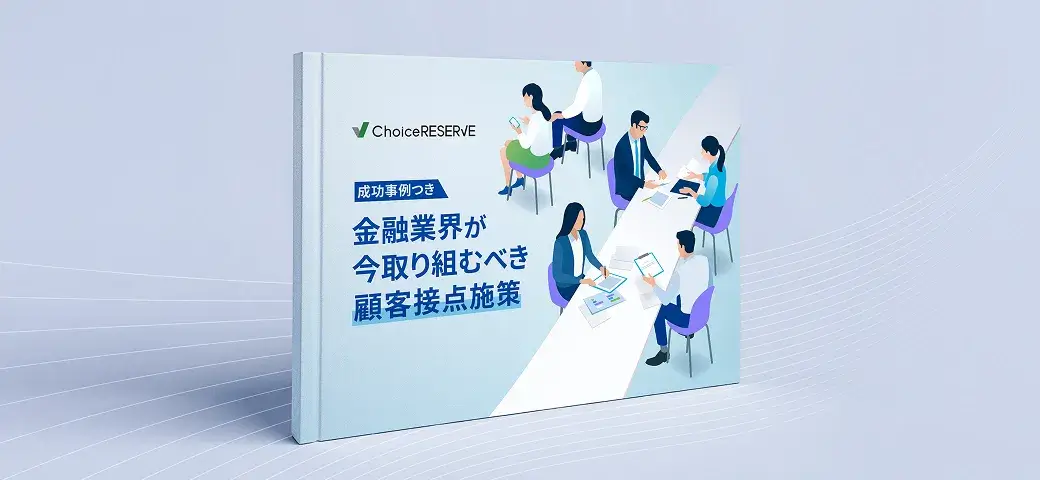- 大学DXは、オンライン授業への移行を契機に、業務効率化や教育の最適化のために不可欠に
- 「予約システム」導入は、大学DX推進の重要な鍵となり、煩雑な予約管理業務を効率化
- DXの推進は、業務効率化だけでなく、学生へのより良い教育提供と大学運営の改善に貢献
新型コロナウイルスの流行をきっかけに、様々な分野においてオフラインからオンラインへの移行が発生しました。DXは一般的に企業が導入するイメージですが、大学などの教育機関においても、多くの授業がオンラインに移行し、従来とは異なる運営が求められるようになりました。
このようなオフラインからオンラインへの移行は大きな負担がかかるものですが、DXによる業務効率化を図るチャンスでもあります。また、学生に対して最適化した教育を提供するという意味でも、重要な取り組みとなるでしょう。
本記事では、大学でDXが求められる理由や推進するメリット、課題をお伝えします。併せて、具体的なDXの種類、取り組み事例、業務効率化のカギとなる予約管理システムなどについても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
大学でDXが求められる理由
大学でDX(デジタルトランスフォーメーション)が求められる背景には、主に「業務効率の向上」と「教育の質の向上」の2つがあります。
近年は少子化に伴う大学進学志願者の減少により、特に小規模大学では入学定員割れが深刻化しています。こうした状況下で運営基盤を維持・強化するためには、コスト削減や業務効率化、志望者確保に向けた取り組みが不可欠となります。そのため、DXを通じて業務を効率化し、限られた資源で持続可能な大学運営を目指す動きが加速しているわけです。
また、教育面においても、学生の学習状況を可視化し、個別最適化された支援を行うには、デジタル技術の導入が重要です。オンライン授業や学習支援ツールの活用、教職員間・学生間の円滑な情報共有などによって、教育の質を高められるような環境を整えることが求められます。
このように、大学におけるDXは、運営と教育の両面での課題を解決する手段として注目されています。
大学におけるDXの種類とサービス

大学におけるDXでは、具体的にどのような施策が求められるのでしょうか。
通常、ビジネスにおけるDXでは、ICT技術を活用して業務プロセスを改善し、ビジネスモデルや組織、企業風土などの変革を行い、ひいては新しい企業価値を創出することを指します。
一方で、大学においては、特に次のようなDXが求められています。
- オンライン授業導入
- ウェビナー導入
- LMS(学習管理システム)導入
- ネットワーク強化
- 予約管理システム導入
- チャットボット導入
それぞれのDXについて、詳細や検討すべきサービスをお伝えします。
オンライン授業導入
オンライン授業導入は、授業を大学の教室内で行うのではなく、ITツールを利用してオンライン上で完結させ、PCやスマホなどの端末でどこからでも授業を受けられるようにする取り組みです。今では多くの大学でオンライン授業が取り入れられています。オンライン授業を実現するツールには、ZoomやGoogle Classroomなどがあります。
ウェビナー導入
ウェビナー導入は、セミナー・講演会をITツールを活用してオンライン上で完結させ、どこからでもセミナー・講演会を聴講できるようにする取り組みです。ウェビナーはオンライン授業と同様に、既に多くの大学で取り入れられています。ゼミや研究室における発表・ディスカッションなどの活動をオンライン化している大学も多いでしょう。ウェビナーを実現するツールには、ZoomやCisco Webexなどがあります。
LMS(学習管理システム)導入
LMS(学習管理システム)とは、Learning Management Systemの頭文字をとった言葉で、学習教材のオンライン配信を行うとともに、学習進捗や成績などを管理・可視化するためのシステムです。近年では授業のサポートツールとして、また学生一人ひとりに最適化した学びを提供するツールとして、LMSを導入する大学が増えています。LMSには、KnowledgeDeliverや光Webスクールなどのサービスがあります。
ネットワーク強化
ネットワーク強化は、ITツール・サービスの利用により増大するデータ通信への対応や利便性強化のためのWi-Fi利用などを行う取り組みです。具体的には、複数キャンパスをつなぐネットワークの回線強化や管理効率化、大学内への無線アクセスポイント設置などがあげられます。複数キャンパスのネットワーク回線強化や管理効率化にはSD-WANなどの技術活用が有効です。
また、大学などの学術機関では、SINET6(学術情報ネットワーク)を利用できます。SINET6は文部科学省推進のもと、回線の高速化と大容量化が進められています。大学における研究に必要なインターネット通信にSINET6を活用することも本取り組みに含まれるでしょう。
予約管理システム導入
予約管理システムとは、オンライン上で予約の受付や管理を行い、申請や予約業務を効率化するシステムです。大学においては、オープンキャンパスなどのイベント参加受付やイベント開催時に利用する教室・共有スペースの利用予約管理などに活用できます。新型コロナウイルスの流行以降、イベント開催において人数制限が必要になったことを受け、予約管理システムを導入する大学が増加しました。予約管理システムにはChoiceRESERVEなどのサービスがあります。
イベントやセミナー、説明会など特定の用途に特化した予約管理システムをご検討中の方は、ぜひ「Tsudle(ツドル)」もご覧ください。
→イベント予約管理システム「Tsudle(ツドル)」はこちら
チャットボット導入
チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、チャット上でのユーザーからの質問に対して自動で応答するプログラムです。主にウェブサイト上に設置され、問い合わせ業務の効率化を目的として導入されます。大学においても、学生や保護者からの定型的な問い合わせを自動化でき、業務効率化および学生・保護者の満足度向上につながるでしょう。チャットボットには、hachidoriやチャットプラスなどのサービスがあります。
大学でのDX取り組み事例

大学でのDXには様々な取り組みがあることを紹介しましたが、具体的な事例としてはどのようなものがあるのでしょうか。いくつかの大学の事例を紹介します。
東北大学
東北大学は、2016年の東日本大震災での教訓を踏まえ、新型コロナウイルス流行以前からDXに取り組んできました。東北大学でまず着手したのは、仮想デスクトップの導入によるリモートワーク環境の整備です。以降もクラウド業務基盤を整備し、ベンダーにとらわれないマルチベンダーなDX基盤を整備しています。2020年には東北大学オンライン事務化宣言を行い、整備したクラウド業務基盤を活用した窓口フリー、印鑑フリー、働き場所フリーに取り組んでいます。
▼取り組みポイント
- 窓口フリー:日本語・英語・中国語の3か国語対応チャットボットを導入し、いつでも誰でもどこからでも各種情報や資料にアクセス可能なオンラインカウンターを実現
- 印鑑フリー:2021年3月時点で126の様式について押印廃止、グループウェアのワークフロー機能を活用して段階的な電子決済への以降を実現
- 働き場所フリー:テレワーク関連の規程・マニュアルを整備し、テレワークおよびフレックスタイム制を制度化
香川大学
香川大学におけるDXは、ベンダーによるシステムに頼らず、「自分たちが本当に必要なシステムはなにか?」を考えた取り組みが特徴的です。DXのためのシステムは導入していますが、必要最小限にとどめています。香川大学が力を入れたのは、自分たちでシステムの要件定義を行い、必要なシステムを内製することです。
具体的な取り組みとして、香川大学は教員・職員のみでなく学生を含めたDX推進チーム、DXラボを立ち上げました。DXラボでは、業務・学生UX調査や業務改善アイデアソンを実施、DXにおける課題を洗い出し、それを解決するためのシステムをローコード開発プラットフォームを利用して内製化しています。
▼取り組みポイント
- 最小限のシステム導入でオンライン化を実施
- DXラボを立ち上げ、教員・職員のみでなく学生を巻き込んだDX推進を実施
- ローコード開発プラットフォームを利用し業務システムを内製
東洋大学
東洋大学では「学生ひとり一人の成長を約束するため、デジタルを十分に活用した学修者本位の教育の実現を目指し、大学全体の教育の高度化と質保証を十全にする。」という基本方針のもとDX推進に取り組んでいます。2021年に東洋大学教育DX推進基本計画を策定し、2022年3月にはCLMS(キャンパス・ライフ・マネジメント・システム)という独自のアプリを学生に配布、学生生活を支援する取り組みを始めています。今後もCLMSを中心に、DX推進が進んでいくでしょう。
▼取り組みポイント
- 教育情報のデータ統合とAI解析、オン・オフキャンパスそれぞれの学習高度化と多様化、リカレント教育の世界展開、FD・SDプログラムの構築、デジタル活用推進体制と外部人材の評価体制構築を含む東洋大学教育DX推進基本計画を策定
- 学生ヒアリングを実施し、DX推進の課題を洗い出し
- CLMS(キャンパス・ライフ・マネジメント・システム)という独自アプリを開発・展開
大学でDXを推進するメリット

大学でDXを推進すると、大学側と学生側それぞれ様々なメリットが得られます。ここでは主なメリットを4つ解説します。
事務作業を効率化できる
予約管理システムなどのツールを導入すれば、授業やイベント、共用スペースの利用などの申請受付をオンライン上で完結できます。オンラインであれば、オフラインと違い窓口があいている時間以外でも申請ができるとともに、受付側も手の空いた時間で申請対応を行うことができます。また、チャットボットによる問い合わせ対応やクラウドサービスによるデータ処理を活用すれば、事務作業の自動化・効率化につながるでしょう。
時間やスペースを効率的に活用できる
授業をオンライン化すれば、学生は授業をどこからでも受けられるようになるため、通学にかかる時間が不要になります。大学側としても遠方からの学生を受け入れやすくなり、学生と大学双方にメリットが得られるでしょう。授業のアーカイブ配信もできるようになるため、授業を後から聞き直すことも可能になります。また、授業がオンライン化されれば授業を行うためのスペースが不要になります。利用しなくなった授業室を別の用途に活用するなど、スペースの効率的な利用にもつながるでしょう。
コスト削減につながる
大学によっては、講演会などのイベントを行う際、他のイベントスペースなどをレンタルしている場合もあるでしょう。イベントをオンライン上で開催できるようになれば、イベントスペースをレンタルするコストが不要になります。
また、大学でイベントスペースを保有している場合でも、毎日イベントを開催しているわけではありません。イベントスペースの利用をオンライン上で効率的に管理できるようになれば、イベントスペースを利用しない日は他の大学や企業に貸し出す、提携している大学間でイベントスペースを共用するなど、コスト面での削減にもつながるでしょう。
最適化した教育を提供できる
LMSを活用すれば、学生一人ひとりの学習状況を可視化できます。学習状況を可視化できるようになれば、学生ごとの学習進捗にあわせて最適化した教育を提供できるようになります。また、LMSサービス提供事業者が用意する最新コンテンツでの学習もメリットと言えるでしょう。大学の授業では実現が難しい、VRなどの映像技術やハンズオンでのトレーニングなど、質の高い学校教育を実現できます。
大学におけるDXの課題

多くの大学がDXに取り組んでいますが、いくつかの課題も浮き彫りになっています。現在の大学におけるDX推進における課題を解説します。
IT人材の確保が難しい
DX推進のためにITツールやサービスを導入しようとしても、使いこなすためにはある程度のITリテラシーが必要になります。IT人材が不足している昨今では人材の確保が難しく、少子高齢化が進んでいく日本では、今後も人材確保が課題になるでしょう。IT人材を確保するためには、大学といえどIT人材を育成する環境を整えていくことが重要になります。
LMSサービスのなかには、UdemyなどのITスキルを身につけられるコンテンツを提供しているものもあります。学生の学習のみではなく、教員・職員の学習環境整備も今後の課題と言えるでしょう。
導入・運用コストがかかる
DX推進によってコストの削減を図ることは可能ですが、ITツールやサービスの導入・運用にはコストがかかるため、DX推進によって削減できるコストとITツールやサービスの利用にかかるコストを照らし合わせる必要があるでしょう。短期的な視点ではなく、中長期的な視点でコストパフォーマンスを意識することが重要です。
コストパフォーマンスを意識するうえで大切なポイントは定期的な効果測定です。導入したITツールやサービスがほとんど利用されていない状況では、得られるメリットよりもコストによるデメリットのほうが大きくなります。導入したITツールやサービスの利用状況をレポートでデータ化し、定期的に見直しを行いましょう。適宜アンケートなどを行い、どのような点が活用における障壁になっているのかを確認すると、次回の導入の参考にできます。
効果がでるまでに時間がかかる
DX推進は、内容によって導入の検討から実際に効果がでるまでに何年もかかる場合があります。特にキャンパスネットワークの整備などインフラ面のDXは、対応が完了するまでの期間が長くなりやすいでしょう。ITツールやサービスの導入においても、導入自体はすぐに行えたとしても、実際にユーザーが利用できるようになるまでには規程や利用マニュアルの整備、ユーザーへの利用説明などが必要になります。DX推進は一朝一夕では行えないため、長期的な視点で考えることが重要です。
大学でDXを推進する手順
大学におけるDXの種類やそのメリット・課題などについては先述した通りです。では、これらを踏まえて、具体的にどのようなプロセスでDXを推進すべきなのでしょうか。
一般的には、以下のような手順でDXを進めるのが効果的とされています。
- 目標設定
- 課題整理
- 計画立案
- 経営陣の承認
- 環境・体制の整備
- 実施
ここでは、各手順について詳細をお伝えします。
手順1:目標設定
まずは、DXによって何を実現したいのかを明確にすることが重要です。DXはあくまで手段であり、その施策によって達成したい目標を具体的に設定する必要があります。例えば、「学生の利便性向上」「既存業務の効率化」「教育の質の向上」など、大学の現状や課題に即した目標を検討しましょう。
改善したいポイントを明確にすることで、学内の理解や協力も得やすくなります。目標設定は、今後のプロセス全体を左右する重要なステップであるため、曖昧にせず的確に行うことが求められます。
手順2:課題整理
次に、現状の業務や教育環境における課題を洗い出します。たとえば「紙ベースの手続きが多い」「教職員間で情報共有が進んでいない」「学生の学習状況が把握しづらい」など、改善が必要な領域を整理し、優先順位を明確にしましょう。
この際、経営陣・教職員・学生など、複数の立場からの視点を取り入れることが重要です。アンケートやインタビューなどを通じて、当事者の声を集めるのも有効な手段です。整理した課題はリスト化し、優先順位の高い項目や、比較的すぐに取り組める項目から着手すると、より効果的にDXを進められるでしょう。
手順3:計画立案
課題が整理されたら、それを踏まえて具体的な施策や計画を立案します。スケジュールのほか、必要となるリソースや想定される費用についても事前に検討しておくことで、より現実的で実行可能な計画になります。
また、導入を検討しているツールやシステムは可能な限り明確にし、全体の見通しを立てておくことが重要です。他大学の取り組み事例も参考にしながら、トラブルや遅延を見越して、柔軟性のあるスケジュールを組むようにしましょう。
手順4:経営陣の承認
DXの推進計画が固まったら、学長や理事会など経営陣からの正式な承認を得る段階に進みます。大学全体に関わる大きな変革であるため、最終的な判断は経営陣の意思決定に委ねられます。
また、新たな取り組みであるDXには、慎重な判断がなされる場合もあります。そのため、予算やスケジュールの妥当性、施策の必要性や期待される効果などを明確に示し、理解と納得を得ることが重要です。
手順5:環境・体制の整備
承認後は、システム導入に向けたインフラの整備や、推進体制の構築を進めます。ITベンダーとの連携や、学内におけるDX推進チームの設置、セキュリティ対策の強化など、技術面・組織面の双方をバランスよく整備することが重要です。DX推進チームの設置にあたっては、専門人材の採用が必要となる場合もあります。その際は、外部委託や専門企業とのパートナーシップを検討するのも有効な選択肢となります。
さらに、DXは大学全体で取り組むべきものであり、経営陣や担当部門だけでなく、教職員や関係者にも十分な情報共有と理解促進を図る必要があります。円滑な運用のためにも、学内での丁寧な周知が求められます。
手順6:実施
準備が整ったら、計画に基づき実施段階へと移行します。必要なツールやシステム、サービスを導入し、策定した計画に沿って着実に推進していくことが求められます。
なお、DXを進める中で「想定よりも浸透しない」「関係者の協力が得られにくい」といった新たな課題が生じる可能性もあります。そのため、段階的に導入を進め、関係者からのフィードバックを反映しながら柔軟に改善を重ねていく姿勢が重要です。実施後も継続的に進捗を確認し、必要に応じて計画を見直すことで、より現場に根付いたDXの定着が期待できます。
大学でのDX推進のポイント

では、大学におけるDX推進の課題をふまえ、どのようなポイントをおさえてDX推進をするべきなのでしょうか。3つのポイントを解説します。
現状の課題を洗い出す
多くの大学では、DX推進の計画を立て、優先して解決したい課題から着手を始めています。DX推進に取り組む際には、まず現状の課題を洗い出しましょう。課題としてあがった項目こそが、現在既に痛みを感じている問題であり、解決によって得られるメリットが大きいものと言えます。
現状の課題の洗い出しができたら、洗い出した課題のなかから緊急性と重要性をもとに優先順位をつけましょう。DX推進の課題で解説した通り、DX推進には長期的な視点が必要です。DX推進を効率的に進めるために、洗い出した課題の優先順位をもとにDX推進の計画を立てるようにしましょう。
サポートの手厚いITツールやサービスを選ぶ
ITツールやサービスを導入する際には、サポートが手厚いかどうかをチェックするようにしましょう。例えばベンダー側が多言語、かつわかりやすい内容の利用マニュアルを用意していれば、大学側で利用マニュアルを整備するコストを短縮できます。また、不明点があってもサポートに問い合わせて解決できれば、IT人材が不足している状況でもカバーがしやすくなります。
サポートが手厚いかどうかは、利用マニュアル・FAQが充実しているか、口コミでプラスの評価が多いか、問い合わせた時のサポートからのレスポンスが良いかなどで判断すると良いでしょう。
コストパフォーマンスを考える
ITツールやサービスの利用には、初期コストと運用コストがかかります。特に運用コストは1ライセンス/月だと少額に思えても、利用数に応じた年額だと少なくないコストになります。コストパフォーマンスを考える際には、継続的に利用する場合のコストや利用拡大した際のコストも考慮する必要があるでしょう。
また、提供事業者によって、初期コストがかかるもの、かからないものがそれぞれあります。初期コストがかからないもののほうが目先のコストは少なくすみますが、重要なのは中長期的な観点でのコストパフォーマンスです。初期コストがかからなくても、その分運用コストがかさむ場合は、かえってコストパフォーマンスが悪くなる場合もある点に注意しましょう。
大学におけるDXの一つに予約管理システムの導入

いまや多くの大学がDX推進に着手しており、授業のオンライン化やLMSの導入が進みだしています。しかし、それに比べて予約管理システムの普及はそこまで進んでいない状況にあります。予約管理システムは、オープンキャンパスや講演会などのイベントへの参加受付、学生との面談予約、空き教室や共用スペースの利用予約、健康診断の受付など幅広い用途で活用可能です。
予約管理システムを活用すれば、時間や場所にとらわれない予約・申請受付が可能になるとともに、利用頻度の低い設備の利用用途見直しなどコスト削減にもつなげられるでしょう。予約管理システムChoiceRESERVEは、豊富な導入実績と手厚い運用サポートで、多くの企業の課題解決を実現しています。新たなDX推進の一歩として、予約管理システムの導入をぜひ検討してみてください。
イベントやセミナー、説明会など特定の用途に特化した予約管理システムをご検討中の方は、ぜひ「Tsudle(ツドル)」もご覧ください。
→イベント予約管理システム「Tsudle(ツドル)」はこちら
予約管理システムを活用し運営の業務効率化を
大学におけるDX推進には様々な取り組みがあり、技術が進歩し続けている現代においては活用できるITツールやサービスの幅も増えています。DX推進は一朝一夕で実現できるものではないため、課題の優先順位に応じて計画的に取り組みを行う必要があります。また、DX推進においてコストパフォーマンスは非常に重要な要素です。
予約管理システムは多くの課題解決に役立つとともにコストパフォーマンスにも優れ、導入しやすいソリューションです。ぜひ本記事を参考に、予約管理システムを活用して大学運営の業務効率化を実現してください。